プロジェクト紹介 Project introduction
高校生でも可能なMPs簡易検出方法の確立と検証
- チーム名「ぶんじマイプラ班」
- ◎学校名/団体名「東京都立国分寺高等学校生物部マイクロプラスチック班」
◎メンバー名「市石 博/小栁 蒼太/幸松 浩然/佐渡 志穂/障子 裕之」
見えないごみと向き合う私たち
私たち「ぶんじマイプラ班」は、現在世界中で深刻な環境問題となっているマイクロプラスチック問題に関心を持った東京都立国分寺高等学校生物部の有志によって、2023年に活動を始めた生物部の活動班です。現在は、15 人のメンバーが在籍し、それぞれが課題に向き合いながら日々の研究活動に励んでいます。
研究を始めたきっかけは,釣りで捕獲した魚をさばいた際に、消化管内にプラスチックごみを発見したことです。その後、東京海洋大学の学生の方からマイクロプラスチックに関するお話を聞く機会を得て、私たちにも何かできることがあるかもしれないと考え、活動を始めました。
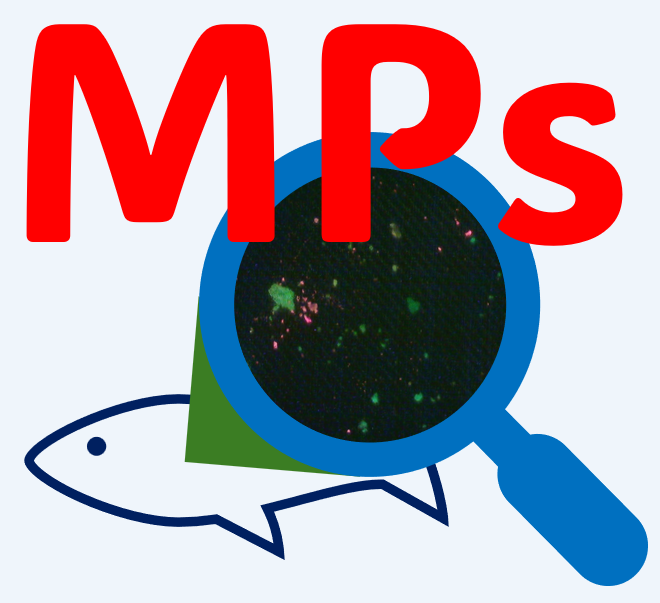
だれでもできる、環境調査へ
具体的な取り組みとしては「マイクロプラスチックの検出方法の開発」、「魚の消化管内からのマイクロプラスチックの検出」の2つを主に行っています。
1つ目の取り組みでは、現在広く用いられている検出方法は、「高価な機器や高度な技術を要するため、高校生が検出を行うことが困難」という問題に対して、容易で精度の高いマイクロプラスチックの検出方法を確立することです。誰でもマイクロプラスチックの検出ができるようになることで、専門的な知識や高価な機器がなくても環境調査が可能となり、より多くの人が身近な環境問題に関心を持ち、行動を起こすきっかけとなります。そしてそれが、マイクロプラスチック汚染データの集積にもつながると考えています。
2つ目の取り組みでは、開発したマイクロプラスチックの検出方法を用いて魚の消化管内からマイクロプラスチックの検出を行っています。これまでにチャネルキャットフィッシュ(採集)、マイワシ(採集)、カタクチイワシ(採集)、カタクチイワシ(煮干)からマイクロプラスチックの検出を行いました。
未来の海を守る仲間をさらに増やしていく
こうした取り組みを行っていく中で、活動を始めた当初は4人だったメンバーが、次の年度には8人に、そして今年度は15人にまで増えました。これからも多くの人に「自分たちにもできることがあるんだ!」ということを知ってもらうために、活動を続けていきます。
